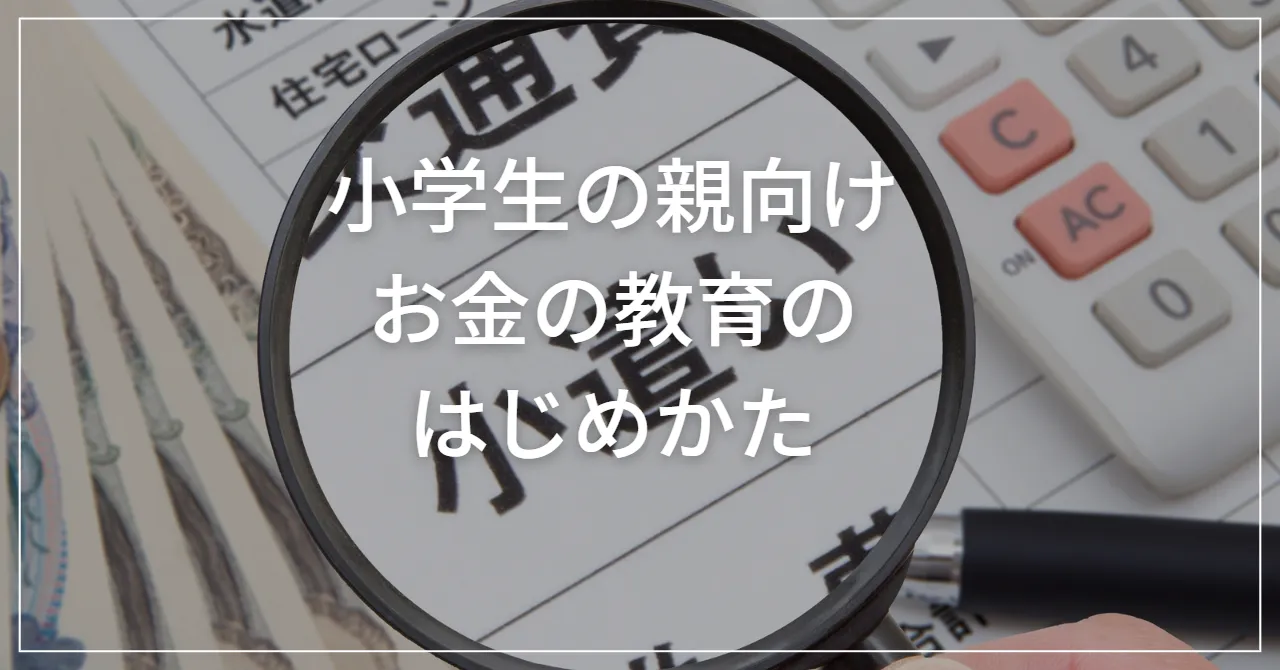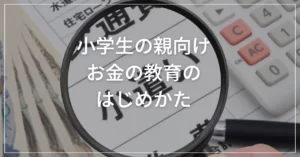小学生になった子どもをもつ親にすすめたい「お金の教育のはじめ方」について紹介します。
最近はキャッシュレス時代になり、子どものお金の教育って、いつからどうすればいいのか?と考えるパパママも増えてきているのではないでしょうか。
最近では、金融庁もお金の教育について本腰をいれて取り組みを推進してきています。
小学生のお金の教育のはじめ方は、一番身近な「お小遣い」が、とても良い機会になりますが、最近では他にも様々な取り組みが行われています。
本記事では、小学生にお金の教育をするための効果的な方法として、小学生のお金の教育から働くことへの意識や、これからの時代に必要な金銭感覚の身に着け方を紹介します。
なぜ小学生にお金の教育が必要なのか
小学生にお金の教育が必要な理由は、将来の人生にとって不可欠なスキルを身につけることができるからです。
お金の扱い方は、将来の生活設計やキャリアアップに大きな影響を与えるため、小学生のうちから正しい知識やスキルを身につけておくことは非常に重要です。
 芝犬
芝犬例えば、お金を使いすぎて借金をしてしまったり、投資や節約の知識がないために将来に不安を感じたりすることを防ぐことができるよ
また、お金の使い方や投資の仕方を理解することで、社会や経済についての正しい知識を身につけ、社会的貢献をすることができるようになっていきます。
さらに、小学生にお金の教育を行うことで、将来的にはより自立した人生を送ることができます。お金を稼ぐ力や貯蓄力、投資力などを身につけることで、自分の将来を自分で切り開くことができるようになります。
以上のように、小学生にお金の教育を行うことは、将来的には個人の生活や社会全体の発展にとっても大きなメリットをもたらすため、必要不可欠なスキルの1つといえます。
小学生にお金の基礎知識を教える方法
お金の基礎知識として、まず、お金の種類や価値、受け渡しの方法について教えるといいでしょう。
お金の種類について
現金と非現金、お金の種類には2つあります。
現金とは、紙幣や硬貨のことで、手渡しで受け渡しができます。
非現金とは、クレジットカードや電子マネー、銀行口座からの振り込みなど、物品やサービスの支払いを現金以外の方法で行うものです。
お金の価値について
お金の価値については、小学生にとっても理解しておくことが大切です。特に、お金を稼いで得たものは、一瞬で使ってしまうこともあります。そこで、小学生にはお金の価値や労働の大切さを教えることが必要です。
以下に、お金の価値についてのポイントを紹介します。
- 労働の価値: お金を稼ぐためには、労働をする必要があります。小学生には、お金を得るためには労働が必要であることを理解させることが重要です。
- 消費と貯蓄のバランス: お金を使うことも大切ですが、無駄遣いをしないようにすることや、貯金することも重要です。小学生には、消費と貯蓄のバランスを理解してもらうことが必要です。
- 購入の前に考えること: お金を使う前に、その商品が本当に必要なものか、価格が適切かを考えることが大切です。小学生には、購入前によく考えることが大切であることを教えてあげましょう。
また、お金の価値は、時間とともに変化することもあります。
物価が上がったり、下がったりすることで、同じ額面でも購入できるものが変化するため、その時の経済状況によって、同じ額面でも価値が変わってしまうことがあるということも教えてあげた方がよいでしょう。
お金の受け渡し方法について
お金の受け渡し方法については、小学生にも理解してもらうことが必要です。
特に、近年はキャッシュレス決済が増えているため、小学生にはこれらの方法も含めて教える必要があります。
以下に、お金の受け渡し方法についてのポイントを紹介します。
- 現金払い: お金を直接渡す方法で、小学生には最も身近な方法です。
- クレジットカード:商品を買うときに、カードをかざして支払う方法です。小学生には、クレジットカードがどのように使われるかを説明してあげましょう。
- デビットカード: 銀行口座からお金を引き出して商品を買う方法です。小学生には、デビットカードがどのように使われるかを説明してあげましょう。
- 電子マネー: カードやスマホなどにお金をチャージして使う方法です。小学生には、電子マネーがどのように使われるかを説明してあげるとよいでしょう。
小学生にお金の管理方法を教える方法


お金の管理を教えるには何にどれぐらい使ったかの収支の記録をつけさせることや、本当に必要な支出なのか?を考えさせることが大事です。
家計簿をつける
お金を管理するためには、まずは収支の記録をつけることが大切です。そのためには家計簿をつけることが一番の近道です。
小学生でも簡単な家計簿をつけることができます。
収入と支出をそれぞれ列に書いて、日々のお小遣いのやりくりを記録しましょう。この記録をもとに、何にお金を使ったのか、どのくらいお金がかかったのかを把握することができます。
家計簿はスマートフォンのアプリや紙に書くなど、さまざまな方法があります。
小学生にとっては、スマートフォンアプリよりも紙に書く方法がわかりやすいかもしれません。
また、家計簿をつけることで、将来の夢や目標に向かって、貯金することもできます。
小さな貯金が大きな貯金になることもあるので、日々のお小遣いのやりくりを家計簿で確認して、貯金にも積極的に取り組めるでしょう。
費用対効果を考える
お金を使うときには、費用対効果を考えることも大切です。
たとえば、小さなお菓子を毎日買うよりも、大きなお菓子を週に1回買ったほうがコストパフォーマンスが高いです。また、買い物をするときには、必要なものと不必要なものを見分ける力も必要です。
小学生にはまだ多くの経験がないため、何が必要かどうか判断することが難しいかもしれません。そんなときは、親に相談することもできるようにするとよいでしょう。
また、費用対効果を考えることで、お金を上手に使うことができます。将来の夢や目標に向けて、お金を貯めるためにも、費用対効果を考えた賢い使い方を心がけましょう。
小学生にお金の大切さを伝える方法
小学生にとって、お金は具体的なものであり、手に取って数えたり、買い物に使ったりすることで、その価値や大切さを理解しやすくなります。
そこで、実際にお金を手に取って、数えたり、買い物に使うことで、お金の価値を身近に感じさせましょう。
お金を数える
小学生にお金を数えることを教えることで、お金の量や種類を理解しやすくなります。
まずは、小銭から始め、1円玉、5円玉、10円玉、50円玉、100円玉、500円玉の順に数える練習をしてみましょう。
また、お札の数え方や金額も一緒に教えることで、より実践的な知識を身につけさせることができます。
商品の価格を確認する
買い物に行くときは、商品の価格を確認することが大切です。
小学生には、買い物リストを作り、商品の価格を一緒に確認することで、商品を選ぶ基準や予算の意識を身につけさせることができます。
また、おつりの計算なども一緒に行うことで、計算力や買い物のスキルも身につけさせることができます。
購入前に価格を比較する
小学生には、同じ商品でも店舗によって価格が異なることを理解させることが大切です。
複数の店舗を回り、同じ商品を比較することで、価格や品質の違いを理解させましょう。
また、商品のパッケージや値札に書かれている情報を読み取ることで、商品の特徴や価格の比較ができるようになります。
店員さんに質問することもできるので、消費者としてのスキルを身につけることができます。
小学生にお金の使い方を教える方法
お小遣いの使い方を教えることは、子どもたちに責任感や自己管理能力を身につけさせる上で大切です。
お金の管理方法や使い方のルールを教えることで、子どもたちが自分のお金を有効に使い、無駄遣いをせずに済むようになります。
お小遣いの管理方法
お小遣いを受け取ったら、まずは家計簿をつけることをおすすめします。
家計簿をつけることで、自分がどのくらいのお金を持っているかを把握し、使いすぎてしまわないようにすることができます。
また、お金を貯めるためには、定期的にお小遣いを貯金する習慣を身につけることも大切です。
お小遣いの使い方のルール
お小遣いの使い方にはルールを設けることも重要です。
例えば、毎回受け取るお小遣いの額を決めたり、お小遣いを使う目的を明確にすることで、無駄遣いを減らすことができます。
また、お小遣いを使う前には、必ず親や保護者に相談することをルールに設けることもよいでしょう。
必要なものと欲しいものを見極める
子どもたちには、必要なものと欲しいものを区別する能力を身につけてほしいものです。
必要なものとは、生活を維持するために必要不可欠なものであり、欲しいものは、その都度購入しても生活に支障がないものです。
例えば、食料品は必要なもの、おもちゃやゲームは欲しいものと言えます。
この違いを理解することは、子どもたちが無駄遣いをせず、お金を節約することにつながります。
必要なものと欲しいものの違いを教える
必要なものと欲しいものの違いを教えるためには、日常生活の中での実例を示すことが効果的です。



例えば、朝食に食べるパンは必要なものですが、パンの種類や味を選ぶことは欲しいものです



冬のコートは必要なものだけど、ブランド物を買うことは欲しいものということも言えるよね
子どもたちには、このような具体的な例を挙げて説明し、必要なものと欲しいものの違いを理解してもらうようにしましょう。
消費者としての意識を高める
必要なものと欲しいものを見極める能力を身につけたら、次に消費者としての意識を高めることが重要です。
子どもたちは、お金を使うことで商品やサービスを購入していることを理解する必要があります。
また、商品やサービスの価値を考えることも大切です。
例えば、同じ機能を持つ商品でも、価格によって大きな差があることがあります。
このようなことを理解することで、無駄遣いをせずに、自分にとって最適な商品を選ぶことができるようになります。
以上のように、子どもたちには、お金を上手に使うための基礎的な知識やスキルを教えることが重要です。
家庭や学校での教育を通じて、将来に向けてお金に関する意識を高め、豊かな生活を送るための準備をすることができるでしょう。
小学生に貯金を教える方法
貯金をするためには、まず目標を設定することが重要です。
目標を設定する際には、貯金する金額や期間、目的などを明確にしておくことが必要です。
例えば、「1年間で10,000円貯金する」といった具体的な目標を設定し、達成するための具体的な計画を立てることが大切です。
目標を達成するための計画の立て方
目標を設定したら、その達成に向けて計画を立てることが必要です。
計画を立てる際には、貯金する金額や期間、貯金のために削減できる出費などを考慮し、具体的なプランを作成します。
また、目標達成に向けた途中段階の目標も設定することで、モチベーションを保ちながら目標達成に向けて着実に進むことができます。
お小遣いの一部を貯金
小遣いをもらっている場合は、その中から一部を貯金するように促すことが大切です。
小遣いの中から貯金する金額を決め、それを毎月コツコツと貯めていくことで、少しずつでも貯金ができるようになります。
また、小遣いの残りを自由に使える分だけ渡すことで、貯金をすることの大切さを教えることができます。
小学生にお金を稼ぐ方法を教える
小学生になったらお小遣いをはじめる家庭も多いと思います。
このお小遣いも「もらう」ではなく、「稼ぐ」方式にするとお金の感覚が身についていきます。
小学生のお金の教育に重要なことは、自動的に入る収入にしないことです。
世界的にベーシックインカム(*1)の議論もされていますが、まだまだ日本社会においてベーシックインカムが施行されることはないですよね。
これは、いまの日本社会にベーシックインカム制度はないため、小学生のお小遣いも毎月自動的に親から与えられるのではなく、まずは労働対価報酬からスタートさせるという考え方です。
※1 ベーシックインカムは、最低限所得保障の一種で、政府が全国民に対して決められた額を定期的に預金口座に支給するという政策
Wikipedia
お手伝い報酬としてお小遣い制度をスタートさせる。それが、小学生のお金の教育に良い影響があると期待しています。
お小遣いを稼ぐ”目的”と”目標を意識させる
子どもには何のためにお小遣いを稼ぐのか、いくらぐらいを目標金額とするのかという目的・目標を設定します。
そうすることで、ゴールを達成する体験をさせることができます。
目標金額は漠然とした金額もよいですが、欲しいおもちゃなど、具体的なモノがいくらで買えるのか?を認識させることも有効でしょう。
そうすることで、子どものモチベーションも維持しやすくなります。
小学生のお金の教育として大事なことは親は財布ではないということ。また、何か欲しいものがあってもMustなのかWantなのかを考える感覚を持つことが大事というのは先ほども記載しました。
加えて、お手伝いによる報酬を得ることで、欲しいものは自分で買うことや何がいくらするのか、それを稼ぐためにはどれぐらい何をしなければならないのかという感覚が身につきます。
また、自分のお金を使うという感覚も身につきますので、無駄遣いが減る効果もあります。
お手伝いは「家族の仕事」をさせる


小学生がお小遣いを稼ぐためには、仕事となるお手伝いも何でもよいわけではありません。
社会に出ても価値ある仕事の対価として報酬が支払われるように、家族の仕事として価値あるものでなければなりません。
理想は、親が不便に思っていたり、やりたいけど忙しくて出来ていないことをみつけて仕事をする。そしてその対価としてお小遣いを支払う。こうすることで、ビジネスの感覚も持ってもらえることが理想です。
ただ、小学1年生ぐらいだと、具体的なタスクを決めてあげたほうがよいでしょう。
支払主(親)が助かることをタスクにしましょう。洗濯物をたたむとか、掃除など手伝いやすさもポイントになります。
ちなみに、家族の一員として、やって当たり前のこと、例えば自分のおもちゃなどの片付けや、配膳などは報酬対象にしないことも決めておくとよいでしょう。
お小遣いを貯めるから、お金を増やす教育へ


お小遣いを稼いで自分でお金を貯めて、目標にしていたものを買うという体験が一通りできたら、次はお金を増やす体験へ移行するとよいでしょう。
働いて貯めるだけでは、お金の教育としては不十分です。稼ぐ方法を見つけ出したり、お金に働いてもらうことを常識的感覚として身に着ける教育にしていくことが、これからの時代に不可欠です。
小学校3年生頃になれば資産運用もスタートさせるとよいでしょう。
子どもに資産運用の感覚を身に着けてもらうことも大事です。
松井証券だと25歳以下の株式取引手数料は無料のため、口座開設をして個別株投資から社会の動向や企業が何をしているのかを学んでもらうこともよいでしょう。
いずれにせよ、子どものうちからお金は貯めるものではなく、増やすものであるという感覚を身に着けさせることもお金の教育としては大事なことです。
これは高校生になると資産形成教育がはじまることから考えても、より早いうちから始めることが大事になります。
関連記事はこちら
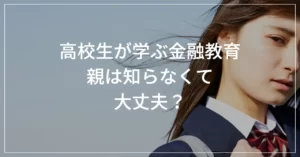
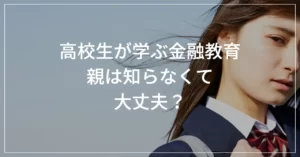
小学生にお金の危険性を教える方法
お金を稼ぐ、貯める、使うと併せて、お金の危険性も同時に教える必要があります。
小学生にお金の危険性を教える方法について、以下のような方法があります。
お金にまつわるトラブルの例を教える
子どもたちに、お金にまつわるトラブルの例を具体的に教えることで、危険性を理解させることができます。例えば、財布を盗まれたり、偽のお金を渡されたり、ネット上で詐欺被害にあったりすることがあることを、事実として伝えましょう。
また、お金を借りることができるクレジットカードやローンについても、返済が遅れるとどのようなことが起こるのか、しっかりと説明しましょう。
現代では、インターネット上でお金にまつわる危険性が増えています。子どもたちに、パスワードの設定やインターネットバンキングの注意点、迷惑メールやフィッシング詐欺などの危険性について教え、安全に利用する方法を教えましょう。
お金にまつわる危険性を理解するためには、親や大人の協力が必要です。子どもたちに、お金に関することで困ったことがあった場合には、すぐに相談することが大切だと教えましょう。
まとめ
小学生にお金の教育は非常に重要です。
文部科学省がまとめた資料によると、小学校でお金の大切さについて学ぶ科目は、5・6年生の家庭科だそうです。この科目では、身近な消費生活や環境について学び、物や金銭の使い方や買物について指導されます。
また、金融教育は、社会においてお金や金融がどのように作用しているのかを理解することによって、自分の生活や社会について深く考えることを指しています。
こういった教育を通じて、子どもたちがお金についての基礎知識を身につけることが重要になっていくでしょう。